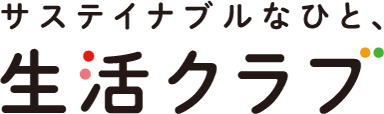【受講者募集】2025年度 神奈川大学・生活クラブ生協寄付講座
生活クラブ神奈川が神奈川大学で、市民の方も参加できる連続寄付講座を開催します。本講座は今年で開催14年目を迎えます。
現代の日本では、経済や社会システムの停滞が格差・貧困など様々な問題を引き起こしています。こうした問題の解決にむけて、協同組合やNPOなどを始めとした「非営利・協同セクター」が多様な活動・事業に取り組んでいます。
本講座では社会動向や歴史的経緯を踏まえながら、協同組合運動の理論や非営利・協同セクターの実践(参加型福祉・たすけあい、ワーカーズ・コレクティブ運動、エネルギー、震災復興など)を学び、社会課題を解決する協同組合と非営利・協同セクターの展望について皆さんと考えていきます。
どなたでも受講いただけます。ご参加お待ちしております。
概要
講座期間:2025年4月9日~7月16日(全14回)時間:毎週水曜日3時限(13:30-15:10) ※5月1日は除く
会場:神奈川大学 横浜キャンパス(横浜市神奈川区六角橋3-27-1) 8号館3階34教室
※キャンパス地図はこちら
参加費:無料
授業科目:神奈川大学 消費生活行政持論「SDGsに取り組む協同組合・市民事業を知ろう」
※講座は実会場(神奈川大学横浜キャンパス)のみで行います。オンライン配信は行いません。
| 日付 | テーマ | 講師 |
|---|---|---|
| 第1回 4/9(水) |
協同組合並びに非営利市民事業とはどのような組織か。出資金や剰余金のあり方、経営の考え方等の原則を、生活クラブ生協の日常の組合員活動を通じて説明します。また、組合員主権とはなにか、協同組合・NPOの参加・運営形態の違い等、本講座を受講するにあたっての基礎学習を行います。 | ①篠崎みさ子/生活クラブ生協理事長 ②出口裕明担当教授 ③篠崎みさ子 |
| 第2回 4/16(水) |
生活クラブ生協が取り扱う品=「消費材」とは何か。産直するためにどのように生産者と提携しているのか。「消費材」の開発、品質などの特徴、今後の課題などについて、鶏肉の生産者からの具体的な事例を通して共有します。 | 籠嶋雅代/生活クラブ生協副理事長 秋川正/㈱秋川牧園代表取締役社長 |
| 第3回 4/23(水) |
レイドロー博士報告「西暦2000年における協同組合」(1980年)が出された時代背景と、協同組合の理念・原則を紹介します。また、同報告書が提起した協同組合の「思想の危機」と危機克服のための4つの優先分野について概説します。その上で、今日の社会をどうみるか、食・経済格差・人口減少・エネルギー等の問題を通して、協同組合の課題と展望に触れます。 | 希代監/生活クラブ生協専務理事 |
| 第4回 5/7(水) |
生活クラブ生協の事業と運動の取組みを、「生活クラブの消費材10原則」等を踏まえ、食料自給や食の安全(添加物、農薬、遺伝子組換え、放射能等)などの取り組み事例を通して、持続可能な開発目標(SDGs)の推進視点を含む共同購入運動や協同組合運動について紹介します。また、消費者、生産者の立場から、食の安全、農業保護、グローバル経済システムについて考えます。 | 柳下信宏/生活クラブ連合会専務理事 |
| 第5回 5/14(水) |
グローバル資本主義は、格差・貧困を拡大し、少子高齢化・人口減少社会、気候変動を引き起こし、更にコロナ禍も引き起こしている原因と言えます。資本主義でもなく国家社会主義でもない、新たな経済のオルタナティブとして注目されるのが「社会的連帯経済」です。民主的な運営によって、人間の生活や自然との共生を重視した経済活動を行うことが特徴です。地域社会で生活に根ざしたオルタナティブな「経済」をいかにしてつくるか。 SDGsを実現するために社会的連帯経済の価値について、またその理念・理論・実践について学びます。 | 柳沢敏勝/明治大学名誉教授 |
| 第6回 5/21(水) |
人と人とのつながりが基本である協同組合は、東日本大震災とその後の復興への取組みにあたり、ネットワーク型の市民活動を通して大きな役割を果たしてきました。活動の経験から培われた支援の考え方および現在も震災復興に取組む「非営利・協同」による実践や課題を学びます。 | 吉田菊恵/公益財団法人共生地域創造 財団事務局長 |
| 第7回 5/28(水) |
生活クラブ生協のエネルギー自給圏づくりに向けた取り組み(脱原発社会、CO2削減、エネルギー自治、再生可能エネルギーの発電施設の建設等)を紹介するとともに、地球温暖化問題を踏まえ、日本の自然エネルギー普及の現状及び環境政策の課題を考えます。 | 佐野めぐみ/生活クラブ生協副理事長 |
| 第8回 6/4(水) |
少子高齢・人口減少社会が急速に進み、私たちは様々な生活リスクにさらされています。今日の社会情勢を踏まえつつ、生活クラブ生協の共済・福祉活動の取り組みを学びます。 また、生活クラブ生協の活動の延長として参画している公益財団法人かながわ活き活き市民基金ならびに一般社団法人フードバンクかながわ等の取組みを紹介します。 |
①矢野克子/生活クラブ生協副理事長 |
| 第9回 6/11(水) |
今日の日本の人口減少社会の特徴と一連の社会保障(介護、医療、年金)改革の課題を概説し、子育てや生活困窮者に対する支援の強化が求められている状況と、公的福祉の限界性を共有します。そして、これからの時代の個人が尊厳をもった生き方・死に方、「参加型福祉」とは何かを問題提起します。 | 半澤彰浩/生活クラブ生協常任顧問 |
| 第10回 6/18(水) |
地域の人の繋がりが薄れ、社会的孤立等の問題が顕在化する中、自発的な市民による居場所や子ども食堂等、だれもが住みやすい地域づくりをめざした社会的自助(相互扶助)型のアソシエーション活動が広がっています。これらの活動の実態調査も踏まえ、アソシエーションが主役の地域社会づくりに向けた課題と展望を共有します。 | 数寄真人/全員参加による地域未来創造機構事務局長 |
| 第11回 6/25(水) |
協同組合原則を基盤とした雇われない働き方であるワーカーズ・コレクティブ(W.Co)とは何か。その歴史、価値と原則、特徴、課題をDVDも活用し学びます。また、市民事業であるW.Coの起業の流れ、事業・運営について事例を踏まえ、居場所・たまり場などの取組みも紹介し、これからの運動のあり方を展望します。 | 井上浩子/一般社団法人 市民連帯経済つながるかながわ専務理事 |
| 第12回 7/2(水) |
困難を抱えた若者たちとの共働・共生をめざす、W.Co協会の誕生経緯、これまでに若者や生活困窮者等を対象とした就労支援事業、居場所や働き場づくり等の取り組みを、「はたらっく・ざま」が日本協同組合学会実践賞を受賞したことも含めて紹介します。またW.Coによる支援の課題や今後の展望について考えます。 | 松川由実/一般社団法人 市民連帯経済つながるかながわ理事 |
| 第13回 7/9(水) |
社会の構成員として一人ひとりの市民が自ら学び養うべき市民性の育成を目的とするシティズンシップ教育にも触れながら、権利擁護・公共政策づくりへの市民参加、政策提案活動などのアドボカシー活動を踏まえ、市民自治のあり方や政治参加の課題について考えます。 | 坪郷實/早稲田大学名誉教授 |
| 第14回 7/16(水) |
①生活クラブ生協職員から、協同組合を形づくっている多様な働き方や意義について考えます。 ②講座全体を振り返り、非営利・協同セクターの今日的意義に関する理解、見識を深めます。 |
①笠原良子/生活クラブ地域生協専務 ②篠崎みさ子/生活クラブ生協理事長 |
〈問い合わせ〉
生活クラブ神奈川 政策調整部
☎045-474-0985(月~金・祝 9:00~17:00)
※この講座に関して、神奈川大学への直接のお問い合わせはお控えください。
【2025年3月5日 更新】
【2025年4月10日 修正】
【2025年4月10日 修正】